前回は、ショーン(2007)の『省察的実践とは何か』の理論に基づいて<行為の中の省察>を考え、実践報告をしました。
それに引き続く第102回の小径でも、<行為の中の省察>をテーマに『実践研究』『実践知』の共有をします。
今、『実践研究』『実践知の共有』が求められていることは、日本語教育学会調査研究推進委員会が実施している2023年度秋季大会調査研究推進セミナーでも明確に述べられています。ここではそれを引用します。
[背景]『日本語教育の参照枠』に基づいた日本語教育環境の整備《日本語教育の参照枠で示された言語教育観》
『日本語学習者=社会的存在(共に社会に生き、共に社会をつくる存在)
⇒『共生社会・社会構築のための言語教育』
⇒『個人や集団が置かれた社会的文脈を踏まえた多様で創造的な言語教育』
<従来の考え方>
×『日本語学習者=単に言語を学ぶ者』
×『言語中心の画一的な言語教育』決まった語彙・文型を決まった順番で
[社会的文脈を踏まえた教育と研究]教育や実践の意味を問う なぜ より意味のある実践へ改善する
求められる実践を問う 社会的文脈 実践知を共有する
何を 実践研究 どのように
言語 教授
💛実践と理論の往還について
実践研究は「事例報告」にとどまらず、実践と理論を結び付け、次の実践へ生かすことが大切です。そして、理論を次の実践と結び付け、次の実践へ生かせることが大切です。
私は、言語学習の省察的実践が、言語学習への信念を育むという理論のもとに実践を行っています。ここでは、自律性が弱い、しかし、友達への愛にあふれ、楽しそうに学ぶ、多様性のある中級後半クラスの<行為の中の省察>を報告し、省察が言語学習への信念を育むことについて考察します。
| 1. 今学期はそれぞれが興味のあることについて<プレゼンテーション>をして、その内容について対話するという活動をしました。その活動で、みなさんの対話力がついていっていると感じています。
1) このプレゼンテーションについてどう感じていますか。 2) 自分の対話力がついてきていると感じていますか。 3) これからの目標は何ですか。 自由に書いてください。 |
💛S.T
まず、プレゼンテーションに対して、面白いと感じている。みなさんは自分が興味をもっている課題を紹介してくれて、楽しいと感じながら、多くのことを学んだ。大したことじゃないけど、このような機会がなければ、私が自分で検索する気がなくて、一生知らないかもしれない。そのため、このようなプレゼンテーションは意味があると考えている。
そして、今回のプレゼンテーションによって、自分の対話力がまだ不足だと感じる。意思疎通だけでなく、きっちり自分の考え方を伝えるのは私の目標だ。また、たまには話しているとき、度忘れの状況がある。それに対して、煩わしいとつくづく感じている。
そのため、これからの目標は自分の言葉を練ることだ。答える前に、「早く答える」という考えを抑えて、「どのように答える」ということをしっかり考えて、適切かつ的確な言葉を言うことを目標として頑張るつもりだ。
💛 G.S
皆のプレゼンテーションは素晴らしかったと思う。いろいろな課題で、さまざまな内容が入っていた。簡単な紹介もあるし、深刻の思いも含まるものもあるし、見事だった。
自分の対話力はまだ不足だと思う。特に、日常対話についての言葉は苦手だ。
それで、次の目標はこの不足に対して強化するつもりだ。N1に合格するかに関わらない。N1に合格するかに関わらない。その後もっと日常用語を覚えようと決めた。
💛S.G
今学期のプレゼンテーション面白いと思う。自分でテーマを探して、自分で紹介します。私は財産権の3つの理論を紹介しました。クラスメートがわからないけれど、自分の対話力が強くなると感じています。これから私はもっと対話を練習して、日本人となんでもしゃべることができるようになりたい。
💛R.K
楽しかったです。でも自分が行ったら、すっごく緊張していた。私はまだまだですね。
今の目標は対話力をもっと練習して、せめて自分の伝えたい、言葉が伝えるように。
💛O.K
今度のプレゼンテーションについては、素晴らしいと思います。たくさん話す機会をもらった。自分の対話力はまだまだだと思います。これからも頑張ります。
🌹多様性のある中級後半の2-1クラスは、学生によって、省察を表現する量にちがいがありますが、省察を繰り返し促し、<待つ>ことによって、省察する<ゆとり>、そして、省察を表現しようとする姿勢が生まれてきたことを、感じています。
<対話する>ことによって、対話のよろこびに気づき、対話への渇望が生まれる。この理論をもとに、私も省察的実践を続けていきます。
遅刻が多いこのクラス、昨日は来ない学生を迎えに、学生たちと家まで迎えにいきました。何度鳴らしても答えないベルを、何度も鳴らし続け、やっと、目覚めて、ドアを開けてくれました。その学生は、私たちがドアの前に立っているのを見ると、驚いたような、照れたような表情をうかべました。そして、身なりを整えて、みんなで日本語教室に向かいました。
2-1クラスのみなさん、日本語教室の小径をともに歩んでいきましょう。
参考文献
日本語教育学会(2023)秋季大会予稿集

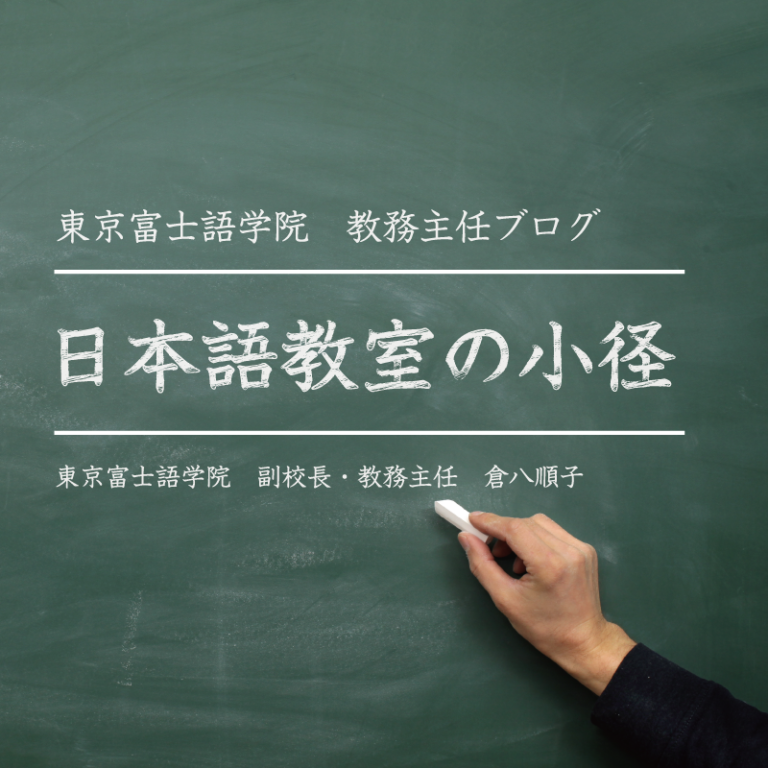
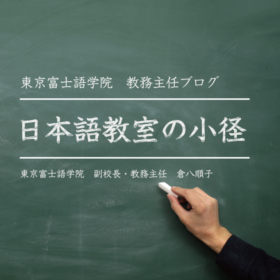
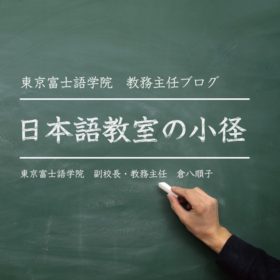
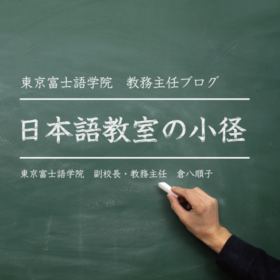
この記事へのコメントはありません。