2024年5月20日(月)は、東京富士語学院2023年度1月生(13名)、2024年度4月生(48名)の入学式でした。会場は『すみだ共生社会推進センター』。この4月からこれまでの『すみだ女性センター』から名称変更しました。女性センターは女性しか使えないというイメージを与える、共生社会を推進したいから」ということでした。多文化共生をライフワークとしている私は、墨田区にはたらくものとして、この姿勢に誇りを感じました。
今回の入学式では、複言語・複文化主義に基づいて、『身体接地した自分のことばで語る』ことを目標としました。新入生はきちんと、ていねいに「はい」ということ。そして、在校生は、自分のことばで伝わるように、他者に向けて語ること。

スピーチに選ばれた3人の在校生は、歓迎のあいさつを、自分のことばで言語化し、からだに入れて、からだから発することを目標として練習しました。そして、当日、身体接地したことばで、楽しそうに、新入生に向けて語っていました。
💛霍玉卓さん
新入生のみなさん、入学本当におめでとうございます。私たちは縁で東京富士語学院に集まりました。今日は重要な日で、節目の日です。私たちはよい時代、色彩とチャンスの時代にいます。
新入生のみなさんが学校に通い始めるとき、みなさんはそれぞれの希望をもっているでしょう。どんな希望でしょうか。
恋に落ちること、卒業後良い仕事につくこと、希望する学校に入学すること、あるいは、毎日を静かに暮らすこと。いろいろあるでしょうが、これらはすべてみなさんの心からの願いです。理想にはさまざまな形があります。努力し、自分の時間に責任もつことを厭わい限り、必ず報われます。
東京富士語学院のみなさん、一緒に楽しく安心して勉強してください。新入生のみなさん、将来の幸せを祈ります。ご入学、本当におめでとうございます。
クリックして霍玉卓さんのスピーチをごらんください。
💛鄒徳浩さん
新入生のみなさん、入学本当におめでとうございます。私たちは、この暖かい風が吹く夏めく時に、縁で東京富士語学院に集まっています。皆さんはおのおのの抱負を抱き、将来の新しい生活を想像して、胸がドキドキしているでしょうか。
過去を顧みれば、私は日本へ来てからもうすぐ一年が経ちます。しかし、この国へ来たばかりの光景は今、尚、はっきり目に浮かびます。日本語は分かったのに、店員さんの読経のような長い敬語に困ったこと。若者が雑談するときスピードが速すぎて全く分からなかったこと。せっかくちょっと慣れたのに、電話での話に自信を失ったこと。それらの困った状況は、多分一生忘れられません。一方、花火が夜空に散ったときの幸せ、夕方の風に当たり静かな街を散歩した時の穏やかさ、また、アニメに出た場所を自ら散歩したときの満足感、というような胸に溢れた素晴らしい気持ちも永遠に忘れられないと思っています。
多分皆さんは私と同じようにいっぱい困ることや楽しいこともあるでしょう。別の国での生活はそんなに簡単ではありません。でも、辛い時があっても、寂しい時があっても、諦めないでほしいです。「もう駄目だ」と思ったとき、今のあなたを顧みてください。あなたはどんな覚悟を、どんな夢を抱えて、この知らない国へ来たでしょうか。そして将来ここでどんなことをやりたいと思ったでしょうか。それを思い出して、頑張り続けましょう。諦めなければ、それはもう進んだことです。
東京富士語学院のみなさん、一緒に楽しく、忘れられない思い出を創りましょう。そして、勉強に励み、輝く未来に向かって進んでいきましょう。みなさんの将来の幸せを祈ります。ご入学本当におめでとうございます。
クリックして鄒徳浩さんのスピーチをごらんください。
💛白愛然さん
新入生のみなさん、入学本当におめでとうございます。東京富士語学院では新しい友だちを作り、新しい知識を得るだけでなく、自分自身を発見し、成長することができます。
皆さんは新しい生活を始めるために、日本に来ました。新しい環境に適応するのに時間がかかります。適応する過程で、孤独感を感じることが避けられません。しかし、孤独感を克服することも、みんなが行うべきことです。
独立成長の過程で、日本語は非常に重要な役割を果たします。就職や進学においても、言語能力は不可欠な要素です。東京富士語学院は私たちに日本語を学ぶチャンスを与えてくれました。このチャンスを活用して、日本語能力を高めてほしいです。
最後にみなさんが、この学校で素晴らしい経験をすること、そして自分自身を見つけ、夢を追い求めることができることを願っています。一緒に学び、楽しい時間を共有できることを楽しみにしています。ご入学本当におめでとうございます。
クリックして白愛然さんのスピーチをごらんください。
🌹その後、2-1、2-2クラスの学生たちは、『日本の詩の美しさ、ひとつひとつの単語のやわらかさ、やさしさを伝える』を目標に、2-1クラスは平安時代の手習い歌の「いろは歌」と「いろはかるた」を、2-2クラスは宮沢賢治の「雨ニモマケズ」を一人一人が、自分伝えたい箇所を選んで、身体に接地させてて、伝えました。
💛2-1クラス
「いろは歌」
いろはにほへと ちりぬるを わかよたれそ つねならむ
うゐのおくやま けふこえて あさきゆめみし ゑひもせす
「いろはかるた」
い いぬもあるけば ろ ろんよりしょうこ
は はなよりだんご に にくまれっこ よにはばかる
ほ ほねおりぞんの くたびれもうけ へ へをひって しりつぼめ
と としよりの ひやみず ち ちりもつもれば やまとなる
り りちぎものの ごだくさん ぬ ぬすっとの ひるね
る るりも はりも てらせばひかる を をいては こにしたがえ
わ われなべに とじぶた か かったいの かさうらみ
よ よしのずいから てんじょうのぞく た たびはみちづれ よはなさけ
れ りょうやくは くちににがし そ そうりょうの じんろく
つ つきよに かまをぬく ね ねんには ねんをいれ
な なきっつらに はち ら らくあれば くあり
む むりがとおれば どうりひっこむ
う うそからでた まこと ゐ いものにえたの ごぞんじないか
の のどもとすぎれば あつさわすれる お おにに かなぼう
く くさいものには ふたをする や やすものがいの ぜにうしない
ま まけるは かち け げいは みをたすける
ふ ふみはやりたし かくてはもたぬ こ こは さんがいの くびっかせ
え えてに ほをあげ て ていしゅのすきな あかえぼし
あ あたまかくして しりかくさず さ さんべんまわって たばこにしょ
き きいてごくらく みてじごく ゆ ゆだん たいてき
め めのうえの たんこぶ み みからでた さび
し しらぬが ほとけ ゑ えんはいなもの あじなもの
ひ びんぼう ひまなし も もんぜんのこぞう ならわぬ きょうをよむ
せ せに はらは かえられぬ す すいは みをくう
クリックして「いろは歌」「いろはかるた」をお聴きください。
💛2-2クラス 『雨ニモマケズ』 宮沢賢治
雨にもまけず 風にもまけず
雪にも 夏の暑さにもまけぬ
丈夫なからだをもち
欲はなく
決して怒らず
いつも静かに笑っている
一日に玄米4合と
味噌と少しの野菜をたべ
あらゆることを
自分を勘定に入れずに
よく見、聞きし、わかり
そして忘れず
野原の松の林の影の
小さなかやぶきの小屋にいて
東に病気のこどもあれば
行って看病してやり
西に疲れた母あれば
行ってその稲の束を負い
南に死にそうな人あれば
行って怖がらなくてもいいと言い
北にけんかや訴訟があれば
つまらないからやめろといい
ひどりの時は涙をながし
寒さの夏はおろおろ歩き
みんなにデクノボーと呼ばれ
ほめられもせず
苦にもされず
そういうものに
私はなりたい
クリックして『雨ニモマケズ』をお聴きください。
🌹体から出たことばは、新入生に届いたと感じられました。
他者の声に耳を傾ける、他者に自分のことばを伝える複言語・複文化主義に基づいた日本語教育を、私なりに考えて、続けていきたいと思います。

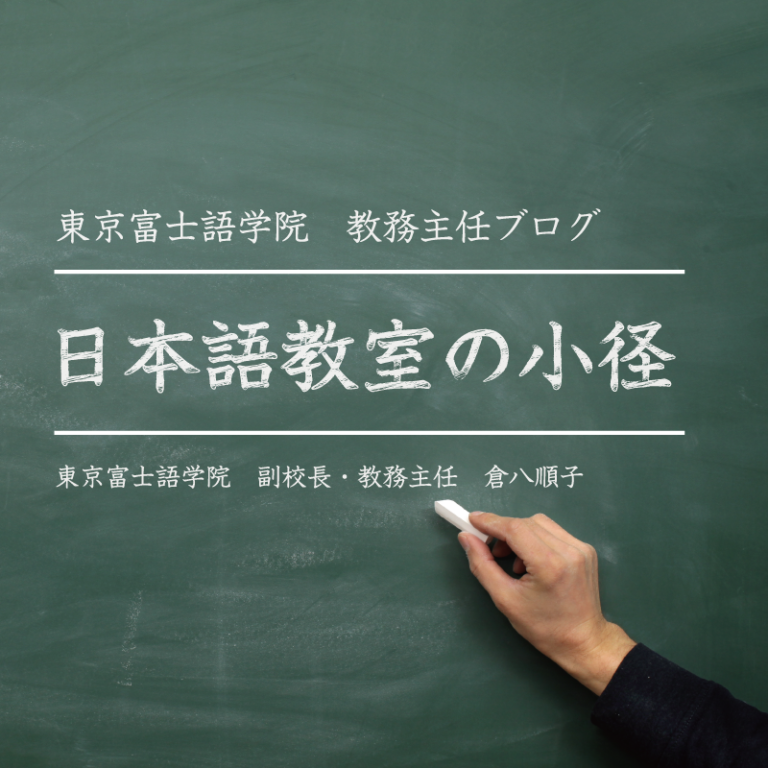
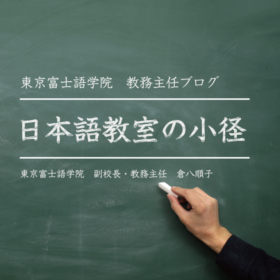
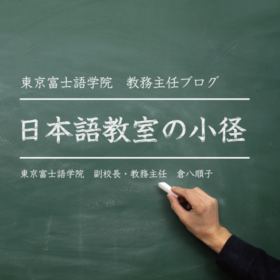
この記事へのコメントはありません。