学びにおいては、自分の学びを省察し、学び方を学ぶことが大切です。このことは、CEFRの5つの考え方にも表れています。教師は、教室を民主的な静かな空間にし、学習者一人ひとりの自律性を育んでいくこと、教室を<協同>と<探求>の空間にしていくことが大切です。また、学習者は、自分の学習を<省察>することが大切です。佐藤(2021)は、ベイトソンの、学びには「知識の内容を学ぶlearningⅠ」(見える学び)と「知識の学び方を学ぶlearning Ⅱ」(見えない学び)があり、より本質的なのはlearningⅡだということを引いたうえで、learningⅡを「真正の学び(佐藤p.85)と呼び、学びにおけるlearningⅡ(探究)の大切さを提案しています。
言語学習における探究の大切さに気づいてから、私は、期末のアチーブメントテストの時間に、私の授業実践の目標とそれに向けてのバックワード・デザインを伝え、学生自らに言語学習について振り返りの省察的作文を書いてもらっています。この実践研究は、私が授業実践をとおして、学生たちのすばらしい変容を感じていること、そして、<自らの行為を省察することによって信念が育まれれる>という理論のエビデンスをとるためでもあります。
本報告では、B1段階、B2段階の学生に対して行った<行為の中の省察>を報告します。
1)B1段階:自律性が弱い、しかし、友達への愛にあふれ、協同によって、対話力がついていった、多様性のある中級後半クラス
作文での問いかけ
| 私は、みなさんが協同して、対話力を身に付けることを目標にプレゼンテーションの授業をデザインしました。
1.自分の興味・関心あるテーマを選ぶ。 2.それを5分程度のわかりやすいPPTにまとめる(ふつう体) 3.ていねい体で10分程度で、わかりやすく、発表する。このとき、わからなければ複言語主義に基づいて母語を用いてもよい。 4.聴いている学生は<静かに>聴き、発表が終わったら、発表者に感想を言い、質問する。すでにほかの人が質問したことは、質問しない。
テストでの<省察的>問いかけ 今学期はみなさんが興味のあることについて<プレゼンテーション>をして、その内容について対話するという活動をしました。その活動で、みなさんの対話力がついていっていると感じています。 1.このプレゼンテーションについてどう感じていますか。 2.自分の対話力がついてきていると感じていますか。 3.これからの目標は何ですか。 自由に書いてください。 |
プレゼンテーションの内容は卒論のテーマ<毛細管について><社会心理学>であったり、<カメラについて><ゲームについて><アニメについて>など自分が関心をもっていることであったり、さまざまです。
全体的に発表者が楽しみながら発表していることが伝わって来ました。伝え方も、日本語に母語を交えたものであったり、あたたかい雰囲気の中で、リラックスして、発表していました。静かなあたたかい空間での、90分の対話の実践となりました。
5人の学生の<省察の作文>を載せます。
💛S.T
まず、プレゼンテーションに対して、面白いと感じている。みなさんは自分が興味をもっている課題を紹介してくれて、楽しいと感じながら、多くのことを学んだ。大したことじゃないけど、このような機会がなければ、私が自分で検索する気がなくて、一生知らないかもしれない。そのため、このようなプレゼンテーションは意味があると考えている。
そして、今回のプレゼンテーションによって、自分の対話力がまだ不足だと感じる。意思疎通だけでなく、きっちり自分の考え方を伝えるのは私の目標だ。また、たまには話しているとき、度忘れの状況がある。それに対して、煩わしいとつくづく感じている。
そのため、これからの目標は自分の言葉を練ることだ。答える前に、「早く答える」という考えを抑えて、「どのように答える」ということをしっかり考えて、適切かつ的確な言葉を言うことを目標として頑張るつもりだ。
💛 G.S
皆のプレゼンテーションは素晴らしかったと思う。いろいろな課題で、さまざまな内容が入っていた。簡単な紹介もあるし、深刻の思いも含まるものもあるし、見事だった。
自分の対話力はまだ不足だと思う。特に、日常対話についての言葉は苦手だ。
それで、次の目標はこの不足に対して強化するつもりだ。N1に合格するかに関わらない。N1に合格するかに関わらない。その後もっと日常用語を覚えようと決めた。
💛S.G.
今学期のプレゼンテーション面白いと思う。自分でテーマを探して、自分で紹介します。私は財産権の3つの理論を紹介しました。クラスメートがわからないけれど、自分の対話力が強くなると感じています。これから私はもっと対話を練習して、日本人となんでもしゃべることができるようになりたい。
💛R.K
楽しかったです。でも自分が行ったら、すっごく緊張していた。私はまだまだですね。
今の目標は対話力をもっと練習して、せめて自分の伝えたい、言葉が伝えるように。
💛O.K
今度のプレゼンテーションについては、素晴らしいと思います。たくさん話す機会をもらった。自分の対話力はまだまだだと思います。これからも頑張ります。
多様性のある中級後半の2-1クラスは、学生によって、省察を表現する量にちがいがありますが、省察を繰り返し促し、<待つ>ことによって、省察する<ゆとり>、そして、省察を表現しようとする姿勢が生まれてきたことを、感じています。
<対話する>ことによって、対話のよろこびに気づき、対話へのあこがれが生まれる。そして、省察することによって、自分の対話力がまだ足りないことを自覚し、学びの実践へのエネルギーとなる、この理論をもとに、私も省察的実践を続けていきます。
遅刻が多いこのクラス、ある日来ない学生を迎えに、学生たちと家まで迎えにいきました。何度鳴らしても答えないベルを、何度も鳴らし続け、やっと、目覚めて、ドアを開けてくれました。その学生は、私たちがドアの前に立っているのを見ると、驚いたような、照れたような表情をうかべました。そして、身なりを整えて、みんなで日本語教室に向かいました。
このことがあってから、遅刻が減りました。また、遅刻しても明るく教室にはいってきて、学びの共同体に自然体で参加しています。
2)B2段階:自律性が育まれているクラス
| 3.今学期の授業では①グループワーク、②プレゼンテーション、③ディベート、④<私の生きる>を書き、暗唱に取り組み、みなさんの発表力ややりとりの力、そして寛容性がつくように取り組みました。
また<省察>の作文を書くことによって、みなさんの目標が明確になるように取り組みました。共同体として、全校校外学習にも行きました。どんな活動が楽しかったですか。みなさんの学びは目標に照らして、どうでしたか。<省察>の作文を書いてください。 |
<省察>のもつ意味を知り、<省察>ができるようになってきた学生たちの<省察>の作文です。テストは90分、課題、1.教科書の読解の問題 2.ボランティア活動<多文化共生>の紹介についての感想を書く作文、3.今学期の活動についての<省察>の作文、でした。90分は内的対話を生む、静かな探究の時間となりました。
S.R.
私にとって、一番楽しかった活動はディベートです。ディベートを通じて、クラスメートと一緒にテーマの内容を話し合い、そして相手の考えを推測し、反論しました。そして、ディベートを通じて、自分の考える力と会話力を高め、実際に日本語を運用するチャンスをもらいました。そして、自分の目標について、全部達成しました。順調に第一志望の大学院に合格し、人生の次の段階に入り、とても嬉しかったです。また、自分のアルバイトを見つけまして、自分の力で生活費を稼いでいます。最後の目標は健康の身体です。今、毎日規則正しく食べて寝て、肉と野菜のバランスを維持して、自分で料理します。今学期は本当に楽しかったです。来年の授業を楽しみにしています。
P.S.
今学期、私たちはたくさんの活動を行い、語学院の授業はてても楽しく、初めて強い参加意識と一体感を感じました。これは、私の学生生活の中で初めてのとても素晴らしい体験です。
例えば、グループディスカッションを通じて、お互いの感想や意見を交換し、同じ問題でも異なる考え方があることに気づきました。「みんな中国からきているのに、こんなに故郷に違いがあるなんて」と驚くこともありました。
私の目標は、N1試験に合格するだけでなく、自分の考えを勇気をもって日本語で表現し、相手の日本語もすぐに聞き取れるようになることです。この目標にはまだ少し距離がありますが、この期間の忙しさが終わった後、また日本語学習に力を入れれば、すぐに自分の望むレベルに達することができると信じています。
O.S.
今学期の授業で最も印象に残っているのは、みんなの発表と校外学習です。
発表では、普段は静かな人でも、自分の興味のある話題になると生き生きと話していて、新しい一面を見ることができました。私自身も発表する機会があり、最初は緊張しましたが、みんなが真面目に聴いてくれたおかげで、自信をもって最後まで話すことができました。クラスメートの発表を聴くことで、様々な考え方や新しい知識を得ることもでき、とっても良い学びの機会になりました。
校外学習では富士急ハイランドに行きました。教室を離れて、クラスメートと一緒に観覧車を楽しんだり、昼食を食べたりしながら、楽しい時間を過ごすことができました。普段の授業で話したことがない面白い話をしゃべることで、より仲良くなれたような気がします。
C.K.
省察とは、この一年間の中に学校の授業からさまざまな活動に参加して、反省します。
私にとtってプレゼンテーションは一番楽しかった活動です。その原因は、みさなんの前に、自分が好きなことをシェアするために、まず多くの資料をまとめて、自分でPPTを作る。その過程はもともと勉強する過程です。
そして、自分が好きなものをほかの人に発表して、ほかの人の質問の中に普段自分が気づかない部分を悟る。その過程も有意義だと思います。
最後の時に、プレゼンテーションの準備、発表、質問を答え、この三部分をサイクルして反省する。不明点と届けない点を練習して、自分の日本語能力がどんどん上がると思います。さらに、自分が好きなものをプレゼンテーションを通じて、同好の人もみつけることができる。
私はこの一年間の学びをして、今以前の目標に照らして、すこしずつ進める。成長はもともとやさしくない。しかし、正しい方法を持ったら、成長はそう難しいこととは言えない。
これから、もっと難しいことがあるかもしれないが、そのようないい方法をしたら、どんな困難も越えると信じている。
Y.K.
今学期の活動を振り返ると、特に楽しかったのはグループワークで行ったディベートであった。クラスメートと意見を交わし、互いの考えを深められたことは、とても有意義であった。また、自分と異なる視点を知ることで、より広い視野で物事を考えられるようになった。
目標に照らしてみると、発表力やコミュニケーション力を向上させるという目標に対して、メンバーと協力して課題に取り組むことができていた。
また、ディベート活動では、相手の主張を聴きながら、自分の意見を論理的に伝える練習ができた。準備する過程では情報を調べたり、整理したりする力が求められ、実際にディベートを行うときには、即興で対応する力も必要である。このようなスキルは、自分の目標である表現力と対話力を高めるという点で大きな助けになったと感じている。
S.M.
今学期は様々な活動に参加して、普通の授業やYouTubeでの学習やアプリの練習でもらえない言語力を鍛錬する機会をもらった。
ちなみにグループワークは含まれていない。私はいつも一人ですべての問いかけを返答でき、グループなんて要らない。特に一年生とほとんど中国人のクラス。母語での喋りが多すぎる。
今最も好きな活動はプレゼンテーション。今まで学んだ言語力を使って、自分の専門と趣味の分野を長い文章で説明するのは挑戦性もあり、実用性もある現実問題を解決する経験。今後専門学校での学習にも予習として役にたっている。私は電気工学の専門学校を選んだが、高校の物理知識は忘れたことが多い恐れがある。こうして、このきっかけに物理を復習して、今後電気専門の学習を準備した。
もう一点は、クラスメートの発表に、実は文字がない時に、単に聴いて理解するのは難しい。その時、効率が低くなる。
R.S.
今学期の授業では、グループワークやプレゼンテーション、ディベートなど、さまざまな活動を通じて多くの学びがありました。全員の意見を言いやすい雰囲気を作ることが大切だと思っています。相手の意見をよく聴いて、柔軟に考えることで、よい結果につながることを学びました。コミュニケーション力と協調性が向上したと感じている。
校外学習では、教室では教えてもらえない内容を得られる。全ての活動を振り返ると、興味ある面によく楽しむことが大切だと思っている。
来年3月卒業することに、学校で大きな成長を感じている。これからも学んだことをいかして、自分のスキルを高め、将来のために役立てることです。
O.R.
今学期は、グループワークやプレゼンテーション、ディベートなどさまざまな活動を通じてたくさんの学びがありました。特にグループワークでは、チームで協力し、意見を出し合うことの大切さを実感しました。自分一人で気づかなかった視点を知ることができ、発想力やコミュニケーション力も向上したと思います。
また、全校校外学習では、クラスメートと一緒に学び、楽しい時間を過ごしました。普段の授業とは違う環境で学ぶことで、新しい刺激を受け、仲間との絆も深まりました。
これらの活動を通して、自分の弱点や成長すべき部分を知ると同時に、達成感や楽しさを感じることができました。今後も目標に向かって努力し、学び続けていきたいです。
R.K.
一番楽しかったのは全校校外学習です。富士山がきれいだし、遊園地はおもしろいし、嬉しかった。もしかしたら、一番難しいのはプレゼンテーションです。今の日本語能力として、発表の原稿を自分で書かなければなりません。辛いと感じます。たくさんの言葉を出せないことがあります。発表を完成しない恐れがあります。
K.S.
今学期は、グループワークやプレゼンテーションを通じて、多くの経験を積むことができました。グループワークでは意見をまとめる難しさと同時に、仲間と協力する楽しさを感じました。自分一人ではきづけないアイディアが生まれる瞬間があり、チームの大切さを学びました。
C.C.
ディベートの活動が楽しかったです。ディベートをするとき、クラスメートたちは本気を出し、自分なりの意見を交換した。いつの間にか、お互いの関係もよくなった。私の学力と目標に照らして、少し、上手になった。
どの<省察>の文章も、学習者の今の考えが表現されていて、<省察>が言語学習への信念をもたす可能性が、示されました。
学内研修で、同僚とこの<省察>の文章を分かち合いました。この学生たちに接していない同僚からは、「本当に自分でかいたのですか!?」という感想がもたらされました。一方、この3か月、授業で彼・彼女たちに接している同僚からは、「こういう授業をしているから、ああいう学生が育ったと納得します。ああいうクラスに育てていかなければならない」という感想がもたらされました。
<省察>のもつ力が示された現在、これからもCEFR A段階のレベルから<省察>を続けていこうと考えています。
引用文献
佐藤学(2021)『学びの共同体の想像ー探究と協同へー』小学館

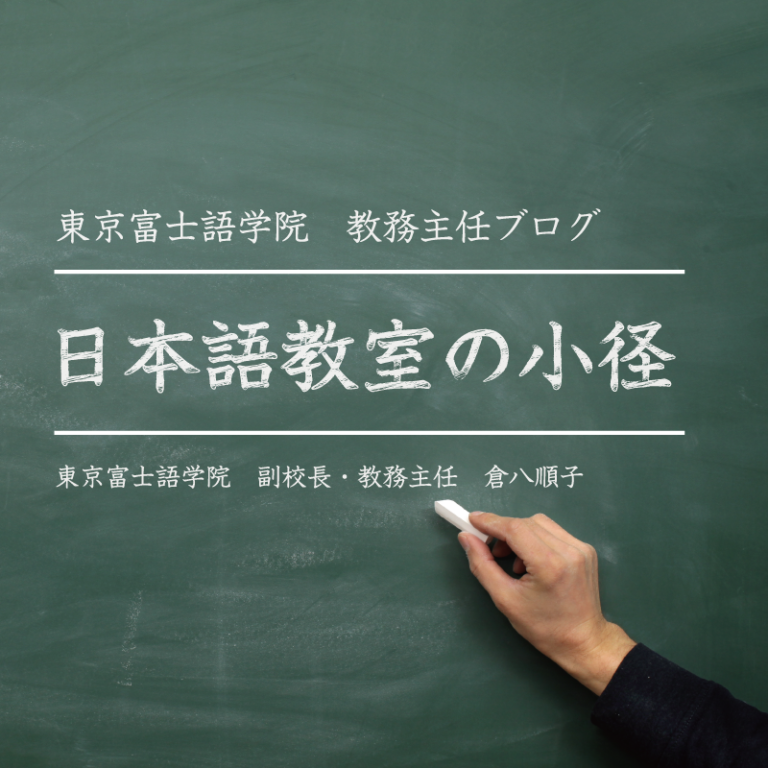
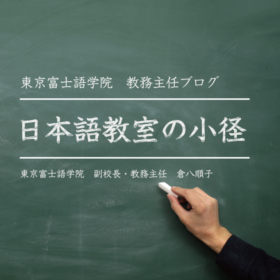
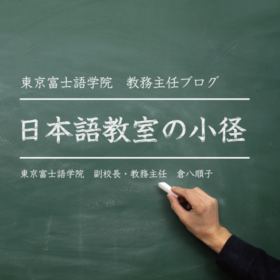
この記事へのコメントはありません。