令和7年、2025年があけました。
日本語教育はこの5年で大きく変化してきました。その変化は<令和>とともにあります。<令和>は、「万葉集五巻梅花の歌32首併せて序」の序文の『時に初春の令(よ)き月、気淑(よ)く風和(なご)み』から採られたものです。この作品は、天平2(730)年の正月13日(太陽暦2月8日頃)に、大宰府の長官である大伴旅人の邸で開かれた梅花の宴で詠まれた歌をまとめたものです。
万葉の奈良の京(みやこ)は、リービ英雄さんによれば、ヨーロッパは暗闇の時代、中国の長安に次いで、スケールだけでなく「文明度」という意味でも世界第二の都市だったといいます。大陸にひらかれていた島国の奈良では、大陸にない感性が大陸にないことばで表され、大陸出身の歌人たちも交じってその表現に参加していました。
万葉の時代は、奈良の住人が、自然界の比喩をもって、自らの言葉で、自文化をおおらかに歌い上げていました。そんな万葉集からとられた元号である<令和>の時代(2019年5月1日~)に、日本語がおおきくひらかれようとしています。それは、長く日本語教育にかかわってきた日本語教師である私にとって、また万葉の時代をこよなく愛する私にとって、大変、うれしいことです。
<令和>に入ってからの、日本語教育にかかわる変化の流れを、時系列に、整理します。
・平成31年(2019年)3月4日文化庁審議会国語分科会『日本語教育人材の育成・研修の在り方について(報告)改定版』
・令和元年(2019年)6月28日『日本語教育の推進に関する法律(日本語教育基本法)』公布・施行
・2020年『言語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠(CEFR)随伴版』
・2021年文化庁文化審議会国語分科会『日本語教育の参照枠』
・2024年4月(文化庁から管轄が変更される)文部加科学省『国家資格 登録日本語教員』『認定日本語教育機関』制度
5年間の経過措置の登録日本語教員の資格を取得しなければ日本語教員にはなれない。
経過措置には6つのルートがあります。参考「登録日本語教員の登録申請の手引き」http://www.mext.go.jp/nihongo_kyouiku/mext02668.html
私自身は、E-1ルートで、講習Ⅰ(5コマ)、講習Ⅱ(10コマ)を受けて、講習修了認定試験に合格(10問中7問以上に正解)すれば、登録日本語教員になれるというコースです。充実した講師陣のもとで、講習Ⅰで、言語政策・多文化共生などの理念、講習Ⅱで、コースデザイン・日本語教育とICT・著作権などの実践は制度について学び、楽しく講習を修了することができました。そして、うれしいことに、登録日本語教員になることができました。
この課程をとおして、学びをデザインすることの大切さ、教師が学習者とともに学ぶ大切さについて、考えることができました。
佐藤学(2021)の『学びの共同体の創造―探究と協同へー』小学館、によると、21世紀の教師は、「教える専門家(teaching professional)」から「学びの専門家(learning professional)」へとその性格を変化させてきていると言います。そこには2つの意味があります。第1の意味は、学び中心の授業になった現在、教師は教える技術や技能よりも学びに関する専門的な知識と実践的な見識がもとめられています。第2の意味は、変化する社会の中で教師自身が学び続けなければまっとうな仕事が出来なくなっているということです。
長い間学びの共同体を本気で創造していきた佐藤学は、『学び続ける教師だけが教職の幸福を教授することができる』(Only learning teachers are blessed with happiness of teaching profession.)ということばを、学びの共同体にかかわる教師たちに、激励のことばとして贈っています。
私自身も、学び続けていきたいと念じています。
引用文献
佐藤学(2021)『学びの共同体の創造―探究と協同へ』小学館
リービ英雄(2002)『万葉集 Manyo Luster』ピエ・ブックス

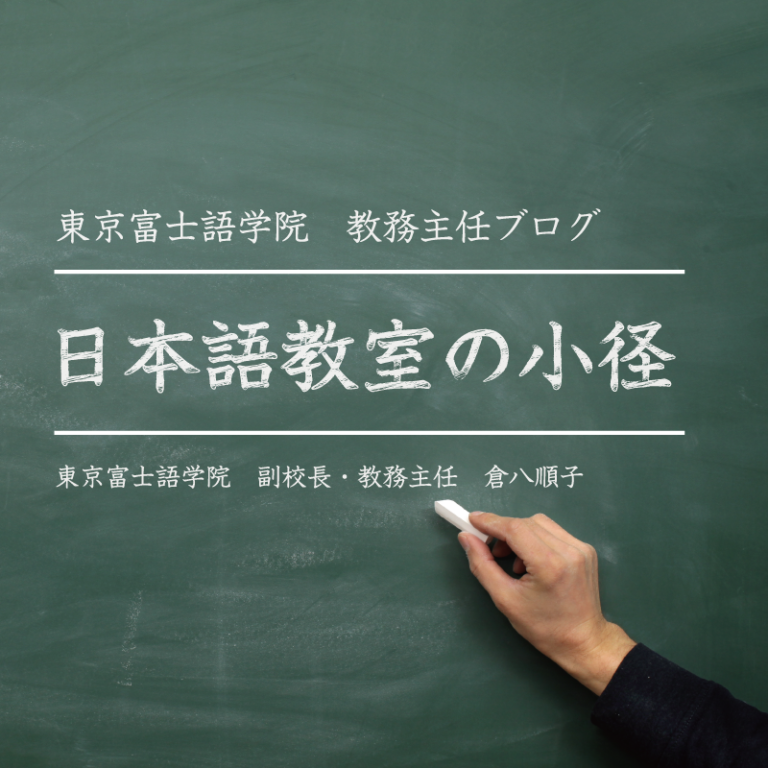
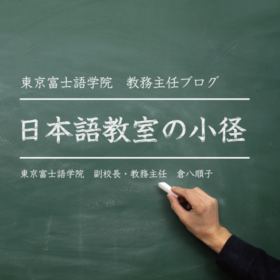
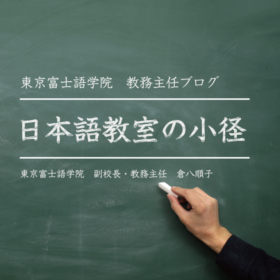
この記事へのコメントはありません。