2024年度は2025年3月19日に第8回卒業証書授与式を行いました。この年の卒業証書授与者は124名、晴れやかに卒業証書を受け取りました。3名の来賓のご出席も賜り、東京富士語学院らしい、あたたかく、やわらかなまなざしに包まれた授与式となりました。


その後、来賓のかたがたに審査員に加わっていただき、卒業生による第8回「スピーチ大会」『日本に留学して成長したこと』を行いました。
総合司会は、卒業クラス2-2クラスで共に学んだ、厳聞憶さんと顧水如さん。出場者は、クラス内選抜を勝ち抜いた20名です。
どれも、自分の留学生活を省察し、言語化し、他者に伝わることばで伝えたすばらしいスピーチになりました。審査のポイントは、主張の明確性、わかりやすさ、発音、声・表現力、暗記、時間(4分以内)、5段階で評価しました。スピーチは、CEFR B2+の能力記述文「聴衆の前での講演Addressing Audience」『はっきりとして、体系的に展開したプレゼンテーションができる。』を目指すものでした。
💛最優秀賞は2-1の『鄒徳浩さん』。全てを暗記し、他者に伝わることばで伝えたすばらしいスピーチになりました。
鄒徳浩さんのスピーチです。
「過ぎた一年を顧みれば、不思議なことに、経験したことをほとんど忘れてしまいました。記憶に残っているのは、断片的な光景とその時抱いていた感情だけです。
2023年6月に、観光客ではなく、留学生としてもう一度この土地に足を踏み入れました。心に溢れた気持ちは興奮ではなく、悩みでした。なぜなら、そのあと、やるべきこととやらなければならないことは、既に明白でした。人々はよく「恐怖は未知から生まれる」と言います。しかし、そのつらい未来を知ったからこそ、心が重くなることもあります。半年でN1に合格し、そして、半年で新しい専門を学んで、憧れの大学院に進学するのは、あの頃乗り越えなければならない山でした。
人間という生き物は、時間が経ったら何でも忘れられるものだと思います。どれほど熱い感情であっても、どれほど真摯な祈りであっても、時が経てば取るに足りない「過去」となり、食後の話題にすぎなくなります。だからこそ、人々は写真や文字が必要なのです。心の奥に封じ込められた感情や記憶を、何かを通じて再び呼び起こすために。私にあの辛い日々を思い出させるのは、家に置かれた暑い本、びっしりと書き込まれた勉強ノート、そして、床に落ちて何度掃いても取り切れなかった髪の毛です。N1に受かるために、私は日本語を生活の隅々まで浸透させました。午前中の授業が終わった後、自習室で夜まで単語を暗記し、家に帰った後、読解を練習しました。そして休憩する時も、日本語の動画しかみませんでした。幸いにN1に合格しました。
しかし、喜ぶひまもなく、塾のクラスが始まりました。研究計画書の準備、新しい専門知識の勉強、慣れない日本の出願方法、これらはすべて私を焦らせました。成果を出せるかわからないが泊まってはいけないという考えが、私の心を満たしていました。こうして、私はまるで機械のように、その日々をすごしました。
大学院の合格通知書をもらった時、嬉しかったかというと、そうではありません。あの頃、別のことに悩んでいました。このように、気づいたら、日本での一年半がすぎていました。
成長したかと聞かれたら、答えは当然です。しかし、私にとって、成長は新しいことを知ったことではなく、既に知ったことを自ら経験することだと感じています。自分で経験しなければ、本当の理解には至らないものです。今の私は、親が言っていた「人生とは死ぬまで次々を悩みが続くものだ」という言葉の意味を充分に理解しました。様々な困難を乗り越えた私ですが、それでもなお、将来の進路に悩んでいます。このことを理解し、受け入れることこそが、この一年半で得た最大の成長だったのかもしれません。
私は、悩みに満ちた生活を続けざるを得ません。それは自分のためだけでなく、他人のためでもあります。私の人生がこれからも続いていくことを願っています。
クリックして鄒徳浩さんのスピーチをお聴きください。
💛優秀賞は2-2の王青青さん。自分の考えを、はっきりと、自分のことばで伝えました。
王青青さんのスピーチです。
「 皆さん、こんにちは。今日は私の留学生活を通じて大切な成長についてお話します。
日本に来たばかりの頃は、すべてが新鮮で、「これも欲しい」「あれも欲しい」という気持ちが強かったです。特に環境に慣れない時期は、買い物でストレスを発散することも多かったです。気づけば、狭い部屋に物が溢れ、逆に気持ちが落ち着かなくなっていました。
転機になったのは、一度衝動買いした服が全く似合わず、仕方なく中古店で売ろうとしたら、もともと安くはなかった洋服は驚くほど安い値段にしかならなくて、「なんてもったいないことをしたのだろう」とすごく後悔しました。
その経験から、買い物するときは本当に必要かよく考えるようになり、持ち物が減るにつれて気持ちもすっきりしました。また、物を買う代わりに、趣味や旅行など、体験にお金を使うようになり、素敵な思い出のほうが自分を幸せにしてくれると実感したのです。
物を持つことより、心が満たされる生き方を知ったこと、これこそが私の留学生活で得た最も大きな成長だと思います。」
クリックして王青青さんのスピーチをお聴きください。
💛敢闘賞は2-7クラスのネパールのアニサさん。ネパールの民族衣装に身をつつんで、ネパールの文化を伝えてくれました。
アニサさんのスピーチです。
「私は2-7クラスのギリアニサと申します。ネパールからまいりました。きょうは私のりゅうがくせいかつについてはっぴょうさせていただきます。
私は2023年7月に日本にきました。私は日本にきたとき、日本語がぜんぜんはなせませんでした。日本人からいわれたこともぜんぜんわかりませんでした。それで日本語がじょうずになりたかったです。私は日本にきたときちょっとこまりました。かいものをするときどうやってみせまでいくのかとかでんしゃにどうやってのればいいのかぜんぜんわかりませんでした。日本のぶんかやルールがわからず、まちがえることもありました。そのときせんせいたちがなにかこまったことがあったらせんせいになんでもきいてくださいといってくれましたので、なにかこまったことがあったらせんせいにききました。日本にきたとき日本はとてもべんりだとおもいました。そのうち、日本でせいかつするのがとてもたいへんだとおもうようになりました。どうしてそうおもったかといえば、日本でせいかつするなら、いちばんたいせつなのは、じかんとおかねだとおもいました。たとえばじぶんのもくひょうがあるとき、じかんとおかねがひつようだからです。みなさんも日本にきたとき、いろいろなこまったことがあったとおもいます。たとえば、日本人とコミュニケーションをとることができなかったことや、いろいろなことのやりかたがわからなくてもやらなきゃいけないことがあるとおもいます。でも、じぶんのやりたいもくひょうのためがんばっていることを、じかくしてせいかつするのが、とてもたいせつなんです。それはじぶんのじょうきょうがたいへんでも、やるきがでなくても、たいへんなことがあっても、じぶんでできるとじしんがもてるとおもいます。
いままで、なんども、あきらめよう、やめようと思いましたが、がんばったおかげでいまのせいかつができます。そして、日本語ができなかった私でもこのようにみなさんの前でスピーチをしています。このわたしのけいけんから、みなさんにつたえたいことがあります。それは、日本でのせいかつをあきらめずにがんばってくださいということです。しっぱいしたり、つらいこともたくさんあると思いますが、あきらめずにがんばれば、なんでもできるとおもいます。
しかし、私がたくさんのゆめをもって日本にきたことや、かぞくも私のゆめをおうえんしてくれていることにきづきました。それからは、なんでもうごかなければいけないとおもい、わからないことをメモしたりして、ひとつずつできるようにしました。日本でのせいかつはわたしにとっても、みんさんにとってもビッグチャンスです。だからじぶんやじぶんのかぞくのあかるいしょうらいのために、いまじぶんにできることをがんばりましょう。いじょうです。ごせいちょうありがとうございます」
クリックしてアニサさんのスピーチをお聴きください。
💛この後、講評いただいた共立女子短期大学の菅生早千江教授は、発表者一人ひとりにあたたかいメッセージをくださいました。対話的なあたたかさが伝わってくる、講評に私も感動しました。

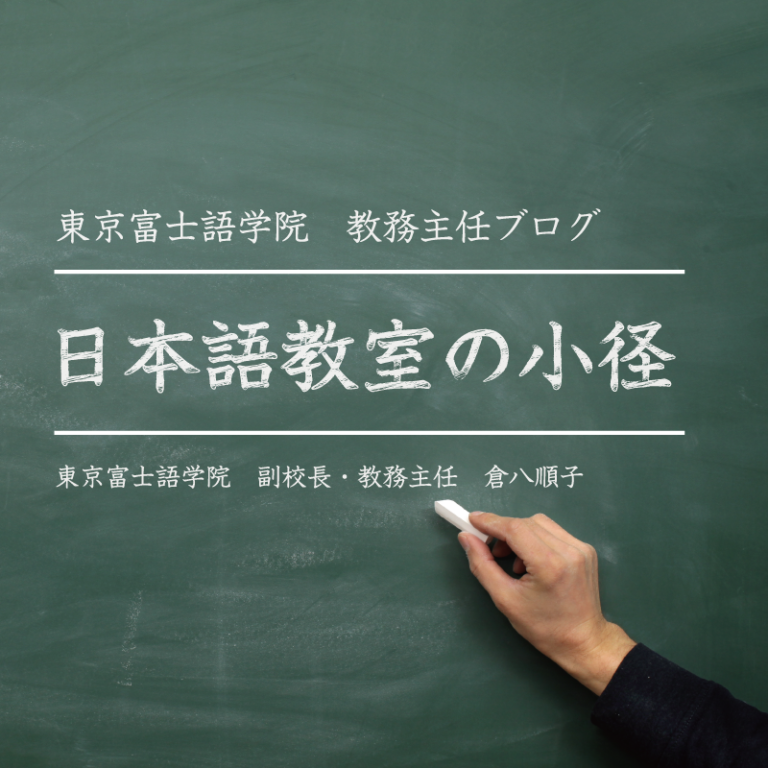
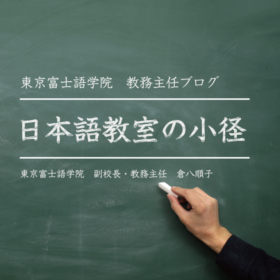
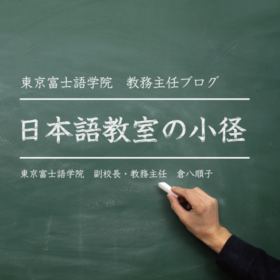
この記事へのコメントはありません。