<対話>が成立するうえでは、<伝えたい>という気持ちが大切です。その<伝えたい>という気持ちはどこから生まれるのでしょうか。
留学生の<対話活動><やりとり>に寄り添って、気が付くこと、それは<伝えたい>という気持ちが生まれるには、<伝わらない>という経験が必要なのではないかということです。<対話>とは、わかりあえないことから、始まるのです。
A2段階の留学生から<対話活動>をしていると、<伝わらない>のです。対話のときの約束は3つ
1.<ゆっくり><はっきり><わかりやすく>
2.漢語ではなく和語で
3.切るところで、切る
ですが、これが、むずかしい。
<伝わらない>経験をした彼・彼女たちには、まちがいなく、<伝えたい>という気持ちが育っていきます。
どうやったら<伝わるのだろう>?????
伝わるためには
1.ペラペラしゃべるのではない。
2.自己紹介がきちんとできる。
3.必要に応じて、大きな声、わかりやすい声で、話すことができる。
何事もそうですが、何かが成立するためには<基礎体力>が必要です。<対話>とは他者とかかわるものですから<他者>に対する<基礎体力>が必要です。
自分の考えが<伝わらない>とき、あるいは自分の考え方で理解してもらえないように思えるときに人は、<なんでわからないのだろう>と<感情的になって>しまうか、<どうせ、あの人にはわからないのだ>とやはり<感情的になって>あきらめてしまいます。
確かに、その作業が必要なこともあります。でも、大切なことは、その自分の感情をいったんわきにおいて、自分の知的積分回路をフルに回転させて、自分を伝えることなのではないでしょうか。
たとえば、<いまは、ニトと受験生の生活です>と、これはB1段階のプレゼンテーションでしたが、私の知的積分回路からは、<二兎を追い続けているのかなあ>と推論して、でも、<ニト?ニト?>と発表者に尋ねながら、私の知的積分回路をフル回転させていました。実はこれは<ニート>だったのです。一人で部屋にこもって、JLPTの勉強を続けているということでした。
異なる価値観と出会ったときに(人はもともとすべてが異なる価値観をもっています)、尊大にも卑屈にもならず、つまり、感情的にならずに、自分の知的積分回路をフル活動させて、共有できる部分を見出していく、その作業は、新しい発見や喜びの作業であることを、私は、日々の対話の実践のなかで感じています。
人の幸福体験には、二種類の幸福体験があって、一つは、ヘドニア;快の喜び、もう一つは、ユーダイモニア;成長の喜び・学びの楽しさがあるそうです(鹿毛:2025)。対話によって、新しい発見や出逢いの喜びがあることは、まさに、ユーダイモニアです。
相手との対話によって、自分のそれまでの意見が変わっていく、それは<対話の基礎体力>がある人に与えられた成長の喜びです。自分の意見が変わっていくことは、<負け>とか<恥ずかしいこと>ではなく、喜びであることを、体感できる環境を与えることこそ、対話教育の目標なのだと思います。
今私は、CEFR,A2段階からB2段階まで、プレゼンテーションとやりとり、の教育実践を行っています。そして、少しずつ、彼・彼女たちに「対話の基礎体力」と対話への<勇気><自信>がついてきていることを実感し、それが彼・彼女たちの喜びとなっていることを感じています。

CEFR B2段階のプレゼンテーションとやりとりの授業


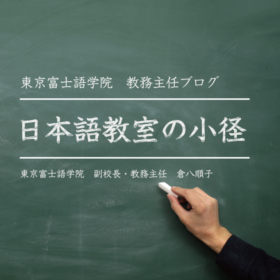
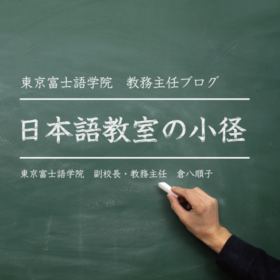
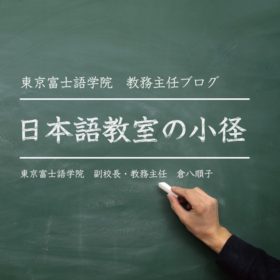
この記事へのコメントはありません。