日光東照宮は、1617年に作られました。江戸幕府を築いた徳川家康がなくなったのが1616年(家康73歳)、その家康の墓を作るために作られました。
私は、1997年に書いた『日本語の表現技術 読解と作文 上級』(古今書院)の第8課で「信長・秀吉・家康 時代を見据える」で家康について次のように著しました。30年近く前のことです。
「家康(1542-1616)は忍耐強い実務家であった。信長が破壊し、秀吉が築いた幕藩体制の基礎を、家康は、忍耐強く、確固たるものにしていった。家康の生涯は、家臣に売られることから始まった。少年家康は3歳で生母と生別したのち、6歳からの12年間を囚われの身としてすごした。・・・天下を取ってからの家康が、徹底的な封建体制をしき、日本人を階級に分けて、その階級から動くことを禁じ、信頼関係のあつい譜代大名を重要視し、信頼関係の薄い外様大名を容赦なくつぶす徳川家中心主義をとったのは、つねに他家のめしを食ってきた悲惨な少年時代の裏返しでもあったのだろう。・・・家康の生涯は、まさに、忍耐の生涯でもあった。『人の一生は重き荷を負うて、遠き路を行くが如し、急ぐべからず、不自由を常とおもえば不足なし、心に望みおこらば困窮したる時を思い出すべし、堪忍は無事長久の基、いかりは敵と思え、勝つことばかり知りて負けることを知らざれば害その身に至る。おのれを責めて人をせめるな、及ばざるは過ぎたるにまされり』。家康の遺訓として知られている」。この遺訓は、家康のお墓につらなる310段の石段の途中に書かれています。
この家康の生き方を留学生のみなさんに伝えたくて、卒業前の校外学習として、ここ4年、日光東照宮校外学習を、留学生の有志のみなさんと実施してきました。押上から東武スカイツリーラインで。もちろん費用は自己負担で。それはとても<意義深い>校外学習だと感じてきました。
その日光東照宮校外学習を、今年は、全校校外学習として、実施することができました。ドアツードアの快適なバス旅行になりました。
2025年6月6日、230人の学生たち、6台のバスに乗り込んで、午前8時に東京富士語学院を出発。私のバスは4号車で1-1クラスと2-2クラス。1-1クラスのリーダーはミャンマーのイーさんとネパールのオリさん。2-2クラスのリーダーは中国の謝路さん。バスに乗り込んだ学生たちは、キラキラとした、はじけるような笑顔でした。




1-1クラスの学生たちは、事前に、何の食べ物をもっていくか、分担していました。ミャンマーのイーさんはミャンマーのラッパットを作ってきました。すばらしい!
日光東照宮では30分ぐらいしか時間がなくて、310段の石段をのぼって家康のお墓に行くことはできませんでした(一部の学生は時間に遅れながら、お墓まで行きましたが!)。
その後、日光江戸村へ。徳川家康が築いた江戸時代の街並みや、江戸時代の文化が体験できるテーマパーク。
新緑の日光江戸村は街道の竹林も杉林も、江戸のそれぞれの町、宿場町、職人の町、商人の町、侍の町、劇場街も、それぞれの表情を再現していて、すばらしかったです。
日本橋では『花魁道中』が。『花魁』とは、デジタル大辞林によると「江戸吉原の遊郭で、新造、禿でなどが遊女郎を「おいらの(己等の姉さんの略)」と呼んだところからという」「位の高い遊女、大夫」ということです。
哀しみをおびた<あでやかさ>が伝わってきました。江戸の町を散策した後、どうしても見たいと思っていた、若松屋で<花魁ショー>をみました。


お大臣様と花魁との<かけあい>に、私のなかからは<笑い>ではなく、<さみしみ>の感情がわいてきました。江戸時代という閉じられた時代の<対話>の形式にふれたことは、私のなかに、<対話>とは何かへの新たな<問い>を生んだのでした。
4号車の帰りのバスで、リーダーの学生たちに、感想を聴きました。

イーさん「私な緑が好きだから、とっても気持ちよかった。楽しかったです」
オリさん「本当に楽しかったです。来てよかったです」
謝路さん「縁あって、一緒のバスになって、みんなで来れて、本当によかったです」
6台のバスは午後6時に無事に東京富士語学院に戻ってきました。
このバス旅行を企画してくれたみなさんに、こころから、感謝します。ありがとうございました。
この<集いの喜び>を、今度は<学びの喜び>に昇華させていきましょう!!
引用文献
倉八順子(1997)『日本語の表現技術 読解と作文 上級』古今書院

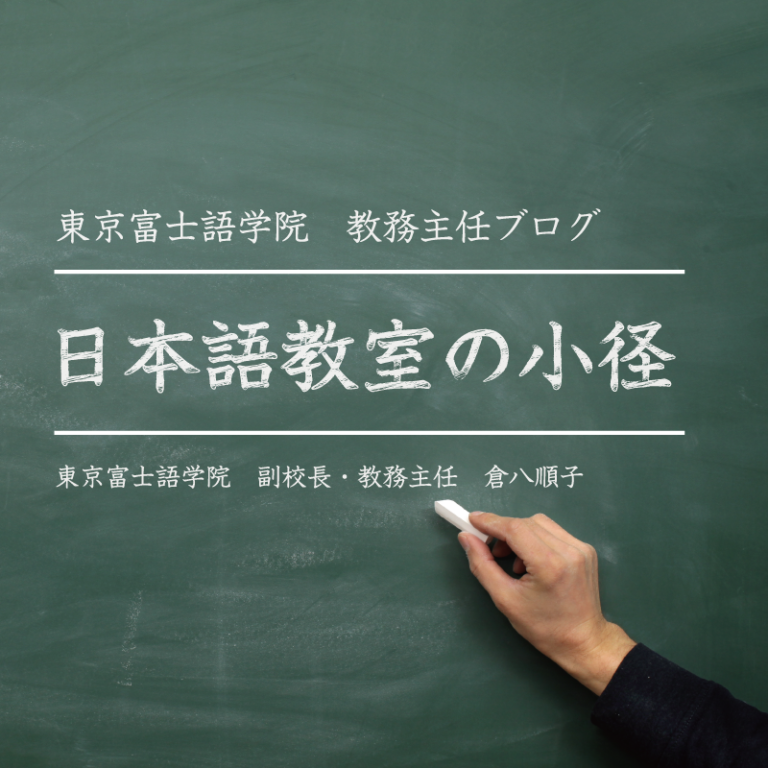
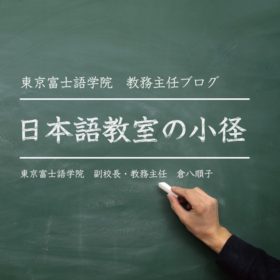
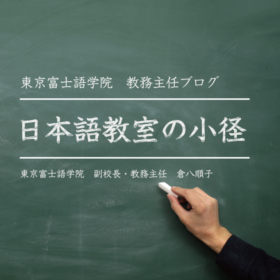
この記事へのコメントはありません。